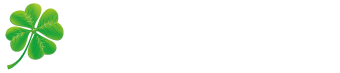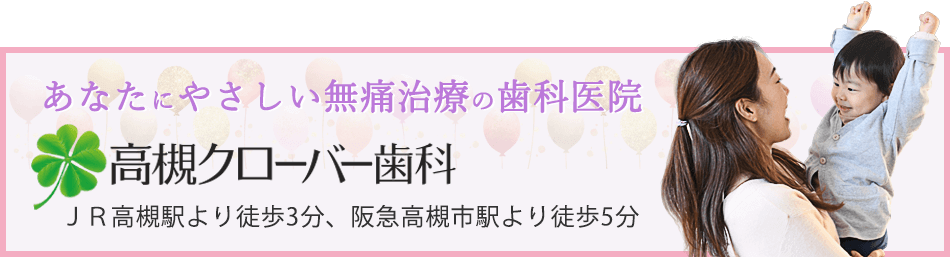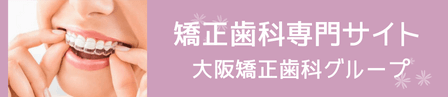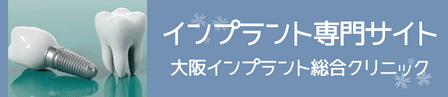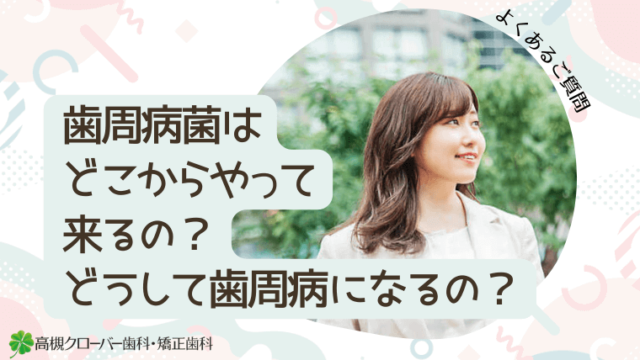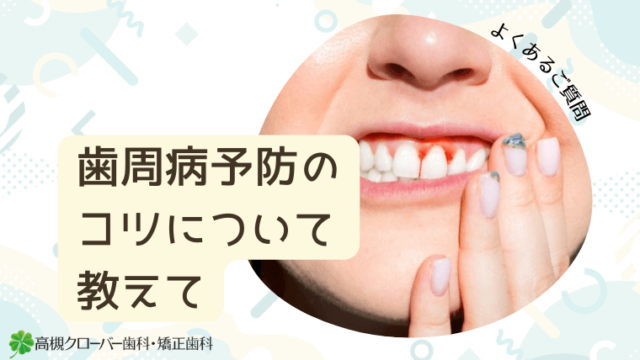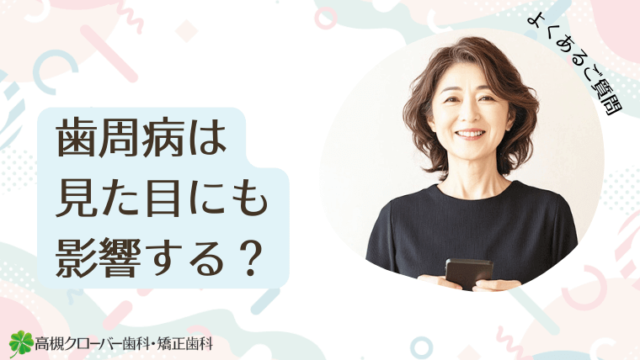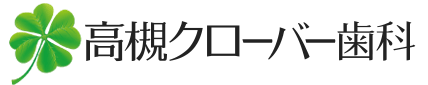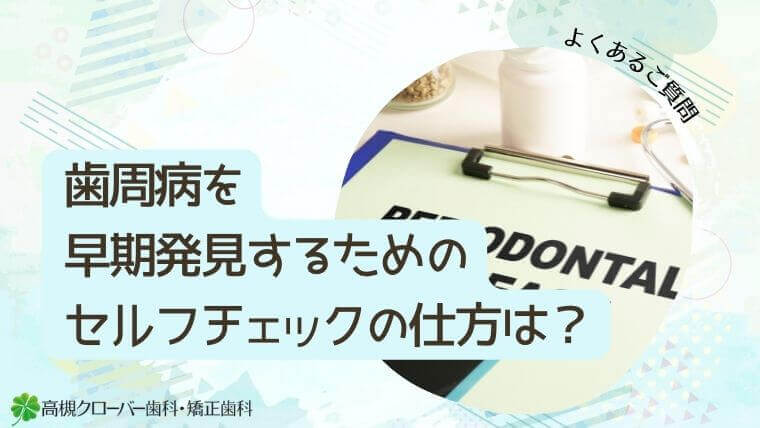
歯周病は初期の間は自覚症状がなく、症状が出はじめた頃にはかなり悪化している病気です。少しでも早く歯周病の兆候に気づいて早期発見をするために、セルフチェックをしてみましょう。
歯周病のセルフチェックをしてみよう

歯周病には虫歯のような痛みは出ませんし、歯肉の内部の組織は外からは見えません。そのため、私たちは歯周病に気づくことが難しく、そのまま放置してしまうことがあります。
歯周病は、初期段階では自覚症状が少なく、気づかないうちに進行してしまうことがあります。以下のセルフチェックを行い、気になる症状があれば早めに歯科医の診察を受けましょう。
歯周病セルフチェックリスト
歯ぐきの状態
- 歯ぐきが赤く腫れている
- 歯ぐきがムズムズする、かゆい感じがする
- 歯ぐきがブヨブヨしている
- 歯ぐきが下がって、歯が長く見えるようになった
- 歯が浮いたような感じがする
歯磨き時の出血
- 歯磨きをすると歯ぐきから血が出る
- フロスや歯間ブラシを使うと出血する
口臭
- 口臭が気になる、または周囲に指摘されたことがある
- 朝起きたときに口の中がネバつく感じがする
歯の動揺
- 以前より歯がグラグラする気がする
- 食べ物を噛んだときに違和感を感じる
歯ぐきからの膿
- 歯ぐきから膿が出ることがある
- 歯と歯ぐきの間から白いものが出てくる
噛み合わせの変化
- 以前より噛み合わせが変わったように感じる
- 以前より歯と歯の間に食べ物が詰まりやすくなった
その他
- 冷たいものがしみる
- 下の前歯の裏側がザラザラしている
- サ行の発音がしにくい
- 歯と歯の間に食べかすがたまりやすい
セルフチェックの結果と対処法
- 1つでも該当する項目がある場合 → 歯周病の初期症状の可能性があります。歯磨きやフロスを丁寧に行い、歯科医院で定期検診を受けましょう。
- 3つ以上該当する場合 → 歯周病が進行している可能性があります。早めに歯科医院で診察を受け、適切な治療を開始しましょう。
- 5つ以上該当する場合 → 歯周病がかなり進行している可能性があります。すぐに歯科医院に相談してください。
歯周病セルフチェックを行う際の注意点
歯周病のセルフチェックは、自分の口の状態を知るために有効ですが、正しく行わないと誤った判断をしてしまうことがあります。以下のポイントに注意しながらセルフチェックを行いましょう。
1. 鏡を使ってしっかり観察する
- 鏡を使い、明るい場所で歯ぐきや歯の状態をチェックしましょう。
- できれば拡大鏡(歯科用ミラーなど)を使うと、細かい部分まで確認しやすくなります。
2. 一時的な症状と慢性的な症状を見極める
- 一時的な症状(例:硬い食べ物で傷ついて出血) → 一過性のものであり、数日で治ることが多い。
- 慢性的な症状(例:歯磨きのたびに出血) → 継続する場合は歯周病の可能性が高いため、注意が必要。
3. 出血や痛みを無理に確認しない
- 出血の有無を確認するために、無理に強くブラッシングするのはNG。
- むやみに歯ぐきをこすったり、爪で押して出血を確認しようとすると、かえって傷つけてしまうことがあります。
4. 口臭のチェックは適切なタイミングで
- 朝起きた直後は一時的に口臭が強くなることがあるため、日中のチェックが理想的。
- 手のひらを軽くカップ状にして息を吐き、匂いを確認。
- デンタルフロスを使った後に臭いを確認すると、歯周病の兆候が分かることがある。
5. 歯の動揺(ぐらつき)を無理に確かめない
- 指や舌で強く押して歯のぐらつきを確かめるのは危険。
- 過度な力を加えると、健康な歯にもダメージを与えてしまう可能性がある。
- 気になる場合は、歯科医院で専門的なチェックを受けることを推奨。
6. 目に見えない部分の異常は見逃しやすい
- 歯周ポケットの深さはセルフチェックでは測れないため、症状がなくても定期的な歯科検診が必要。
- 痛みを感じにくい病気なので、「痛くないから大丈夫」と思わないこと。
7. 症状が軽いからといって油断しない
- 初期の歯周病は自覚症状が少なく、セルフチェックでは異常が分かりにくい。
- 軽度の出血や歯ぐきの腫れがあれば、早めに歯科医の診察を受けるのがベスト。
8. セルフチェックと歯科受診を組み合わせる
- セルフチェックはあくまで「目安」であり、確定診断にはなりません。
- 3〜6ヶ月に1回の歯科健診を受けて、専門的な診断とクリーニングをしてもらいましょう。
歯周病とは
歯周病は歯と歯茎の隙間に歯垢(プラーク)や歯石がたまることで細菌が繁殖して歯肉に炎症を起こし、歯周組織がどんどん破壊されていって、最後には歯がグラグラになって抜けてしまうという病気です。
自覚症状が殆どないのが特徴で、気づいた時にはかなり歯周病が進行した状態になっており、歯をどんどん失っていく怖い病気です。
歯周病は歯を失う最大の原因
歯周病は日本においては国民病といってもいい疾患で、「歯科疾患実態調査」(2016年厚生労働省)では、中等度以上の歯周病患者数は過去最高になりました。
歯周病の分類「グレード」とは?
歯周病の進行を表す分類に、「グレード」というものがあります。
- グレードA【遅い進行】・・歯槽骨が溶ける状態が5年以上ない
- グレードB【中程度の進行】・・5年で歯槽骨の高さが2ミリ未満低くなる
- グレードC【急速な進行】・・5年で歯槽骨の高さが2ミリ以上低くなる
歯周病を予防するための注意点
歯周病を引き起こしやすいのは、細菌の塊である歯垢が歯に付着している状態です。つまり、歯磨きで歯垢を除去すれば口内の細菌の数が減りますので、歯周病を予防することが出来ます。
ただ、単に歯ブラシで歯面を強く磨いたり、長く磨いただけでは歯垢を完全に除去することはできません。そればかりか、歯垢を除去しようと力任せに磨いた結果、逆に歯や歯茎を傷つけてしまうこともあるので注意が必要です。
歯磨きは食後すぐ行うのが理想的です。食事の後は、口腔内細菌が活発に活動するタイミングでもあるからです。
毎日、または毎食後に歯磨きをしているにも関わらず虫歯になりやすかったり、歯周病になってしまう方がおられます。その場合は歯磨きの仕方に問題があり、部分的に歯垢を取り残している可能性が高いため、正しい歯磨きの仕方を歯科衛生士から指導してもらい、実践するようにしましょう。
正しい歯磨きの仕方をマスターしよう
家庭でできる虫歯や歯周病の予防は、毎日の正しい歯磨きです。使いやすい歯ブラシを選び、歯科医師や歯科衛生士の指導を受けて、自分の口内の状態にあった正しい歯磨きの仕方をマスターしましょう。
歯ブラシだけで磨けないところは、歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助清掃用具も活用します。特にデンタルフロスを使えるようになると、歯と歯の間や歯と歯茎の間の溝部分から歯垢を除去出来るようになります。
まとめ

歯を失う原因の1位は歯周病です。歯周病は初期の段階では殆ど自覚症状がないために、気が付けば重症化していて歯がグラグラになってしまっていることも珍しくありません。
歯周病を起こしているのは歯と歯茎の間の溝に溜まる歯垢の中にいる細菌です。そのためお口の中の清掃をしっかり行うことが予防になります。
ご家庭でのセルフケアの他に、定期的に歯科医院でクリーニングを受けるようにすると、歯周病はかなり予防出来ます。